リスク認識が事業継続力強化(ジギョケイ)の土台
1. 事業継続力強化の定義
「事業継続力強化」とは、自然災害または通信その他の重大な障害(自然災害等)が発生した際に、事業活動への影響を軽減し、事業を継続できる能力を高めるための事前対策を講じることを指します。
2. 被害想定の必要性
中小企業が有効な対策を講じるためには、発生しうる自然災害等について自社事業への影響を具体的に想定することが欠かせません。
被害想定は「STEP 2:災害等のリスクの確認・認識」に該当し、ジギョケイの核となる分析工程です。
II. STEP 1:自社を取り巻く「事象(リスク)」の特定
1. 想定すべき事象の種類
暴風、豪雨、地震、津波、噴火といった自然災害に加え、サイバー攻撃や感染症など、人為的・社会的要因によるリスクも含めて検討します。
2. ハザードマップ等の活用による事象の認識
地方公共団体が提供するハザードマップや、国の地震動予測地図などを用いて、自社所在地や供給網に関わる地域の災害リスクを確認します。
3. 甚大な影響を与える事象の選定
すべてのリスクを同列に扱うのではなく、事業活動への影響が特に大きいものを一つ以上選定し、重点的に検討することが重要です。
III. STEP 2:事業活動における「脆弱性」の洗い出し
1. 脆弱性の定義
脆弱性とは、特定のリスクが発生したときに、被害を拡大させる要因となる自社の弱点を指します。
2. 4つの経営資源に基づく脆弱性分析
被害想定の基礎となる脆弱性は、次の4分類で整理します。
- ヒト(人員):特定の人しか業務を遂行できない、感染拡大時にリモート勤務体制を確立していない。
- モノ(建物・設備):耐震・浸水対策が不十分、非常用電源が未整備。
- カネ(資金繰り):保険・共済による補償体制が未整備、売上減少時の資金繰り対策が不十分。
- 情報(データ・システム):バックアップ未実施、セキュリティ対策の遅れ、アクセス権限の管理不足。
IV. STEP 3:「事象」と「脆弱性」の掛け合わせによる被害想定
1. 被害想定の原則
被害想定とは、「想定される事象」と「自社の脆弱性」を掛け合わせた結果として、発生しうる影響を定義する作業です。より深刻な影響を想定しておくことで、効果的な事前対策が導き出せます。
2. 具体的な想定事例
- 事例1:地震リスク
- 事象:地震による大きな揺れ
- 脆弱性:耐震補強が未実施
- 影響:建物損壊により生産ラインが停止
- 事例2:資金繰りリスク
- 事象:感染症による移動制限
- 脆弱性:資金調達の余力不足
- 影響:資金繰りの悪化により雇用維持が困難
- 事例3:サイバーリスク
- 事象:サイバー攻撃を受ける
- 脆弱性:セキュリティ対策未導入
- 影響:取引停止・情報漏えい・信用失墜
V. まとめ:被害想定から事前対策へ
被害想定によって浮かび上がったリスクは、次の工程である**「STEP 4:事前対策の検討・実施」**につなげます。
「どの被害を防ぐか」「どの程度まで許容できるか」を明確化し、優先順位を立てた上で、実効性のある対策を講じることが重要です。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。

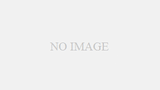
コメント