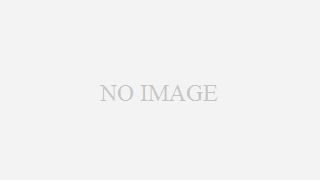学校設置者等とは
「学校設置者等」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS)において、安全確保措置の実施が義務対象となる事業者を指します。この定義は、法第2条第3項に定められています。
1. 学校設置者等の法的定義と義務の根拠
学校設置者等に法的義務が課される背景には、以下の理由があります。
- 認可・監督体制の明確性:法律に基づく認可等を受けて児童等に対して教育、保育等を提供する事業であるため、対象事業者の範囲が明確であり、問題が生じた場合の監督等の仕組みが整っている。
- 児童側の選択の困難性:義務教育段階の学校や、行政措置によって入所等が決まる施設等は、児童等側が安全確保措置等が講じられていない施設・事業を避けることができないため。
学校設置者等は、児童等に対する教育、保育等の役務を提供する立場にあり、教員等による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有しています。
2. 対象となる施設及び事業の範囲
学校設置者等が設置・運営する施設または事業は、主に以下の3つの分類に分けられます。
| 分類 | 施設・事業の具体例 | 根拠となる法分野 |
|---|---|---|
| 学校教育法関係 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)など(大学を除く)。 | 学校教育法 |
| 認定こども園関係 | 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園。 | 認定こども園法 |
| 児童福祉法関係 | 児童相談所、保育所、児童館、児童養護施設、乳児院、指定障害児入所施設等、児童心理治療施設、児童自立支援施設など。 | 児童福祉法 |
| 児童福祉事業 | 指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、家庭的保育事業等、登録一時保護委託者。 | 児童福祉法 |
3. 負うべき安全確保措置の義務
学校設置者等は、教員等(法第2条第4項)による児童対象性暴力等の防止のため、以下の措置を含む安全確保措置を講じる義務があります。
- 犯罪事実確認:教員等が特定性犯罪事実該当者であるか否かについて、国が交付する犯罪事実確認書による確認を実施します。
- その他の安全確保措置:早期把握、相談、調査、保護・支援、研修(座学と演習を組み合わせたもの)の実施。
- 防止措置:犯罪事実確認の結果や調査等を踏まえ、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(原則、対象業務に従事させないことなど)を講じます。
- 情報管理措置:犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置。