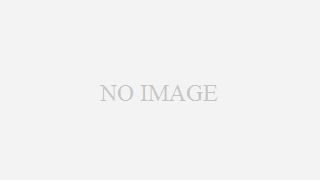特定性犯罪事実該当者とは
「特定性犯罪事実該当者」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS)において、特定性犯罪を犯した経歴があり、その期間が確認の対象となる者として定義される用語です。
この制度の目的は、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する教員等および教育保育等従事者について、特定性犯罪事実該当性の有無を国が事業者に提供する仕組みを設けることにあります。これにより、事業者が雇用時・従事時の安全確保措置を適切に講じることが可能となります。
1. 特定性犯罪事実該当者となる期間
特定性犯罪事実該当者(該当者)は、以下のいずれかに該当する者と定義されます。
- 拘禁刑(懲役・禁錮):その執行終了等から20年を経過しない者。
- 拘禁刑の執行猶予者:特定性犯罪について執行猶予を受け、裁判確定日から10年を経過しない者。
- 罰金刑:その執行終了等から10年を経過しない者。
事業者は、従事者について、この該当性に関する情報が記載された「犯罪事実確認書」により確認を実施します。
2. 特定性犯罪事実該当性が認められた場合の措置
犯罪事実確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、事業者は、過去のエビデンスから性犯罪の再犯リスクが高いことを踏まえ、原則として児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認める」ものとして取り扱うことが適当とされています。
この「おそれがある」と認められた場合、事業者は児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(防止措置)を講じなければなりません。防止措置の内容として、原則、当該従事者を対象業務に従事させないことが求められます。
- 新規採用の場合:内定取消しなどの雇用契約上の措置。
- 現職者の場合:対象業務以外への配置転換や勤務制限の措置。
3. 雇用管理上の留意点
特定性犯罪事実該当性に基づく防止措置として、内定取消し・解雇・配置転換等の雇用管理上の措置を講じる際には、労働法制上の留意点を遵守する必要があります。
特に、採用過程において特定性犯罪の前科の有無を明示的に確認していない場合、犯歴のみをもって直ちに解雇することは難しいと考えられています。そのため、事業者は、あらかじめ以下のような法令適合的対応を行うことが推奨されます。
- 内定通知書や就業規則等に「重要な経歴の詐称」を内定取消し・解雇事由として明記しておくこと。
- 採用募集要項に「特定性犯罪前科がないこと」を明示すること。
- 採用面接や雇用契約締結時に、犯罪事実確認制度の趣旨を説明し、同意を得ておくこと。
このような事前準備と透明性の確保が、児童の安全と従事者の人権の双方を守るために不可欠です。