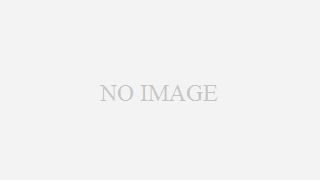日本版DBS(こども性暴力防止法)は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)の通称です。
この法律は、児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う者に対し、
児童対象性暴力等の防止措置を講じる責務を明らかにしています。
制度の核となる義務
法の対象事業者(学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者)が講じるべき措置は、主に次の4つの柱から構成されます。
- 安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修):
事業所における児童対象性暴力等の未然防止と、発生時の適切な対応を実施します。 - 犯罪事実確認:
教員等または教育保育等従事者が、特定性犯罪を犯した特定性犯罪事実該当者であるか否かについて、国が提供する情報により確認を実施します。 - 防止措置:
調査や犯罪事実確認の結果を踏まえ、児童対象性暴力等を防止するための措置(雇用管理上の措置等)を実施します。 - 情報管理措置:
犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書およびその記録)を適正に管理し、目的外利用・第三者提供が厳格に禁止されます。
民間教育保育等事業者の認定制度
学習塾、放課後児童健全育成事業、認可外保育事業等を行う民間教育保育等事業者は、
学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定等を受けることができます。
認定基準には、次のような項目が含まれます。
- 犯罪事実確認を適切に実施する体制の整備
- 安全確保措置の実施(早期把握、相談、研修など)
- 児童対象性暴力等対処規程の作成
- 情報管理規程の策定と遵守
対象となる従事者の判断基準
犯罪事実確認の対象となる「教員等」および「教育保育等従事者」の範囲は、
当該業務が支配性・継続性・閉鎖性の三要件をすべて満たすかによって判断されます。
例えば、次のような職種は対象となり得ます。
- 日常的な送迎業務で他の職員が同席しないバス運転手等
- 他の職員が同席しない児童等との面談を日常的に行うスクールソーシャルワーカー など
行政書士事務所POLAIREのサポート
行政書士事務所POLAIREでは、令和8年12月の制度運用開始に向け、民間事業者の皆様の認定申請や、複雑な情報管理規程の策定、労働法制を踏まえた防止措置の運用設計を支援しております。