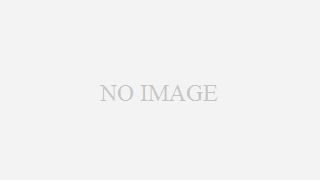不適切な行為とは
「不適切な行為」とは、児童対象性暴力等(性暴力)そのものには該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながりうる行為を指します。事業者がこの「不適切な行為」の段階で適切に対処することで、児童対象性暴力等そのものの未然防止につなげることが重要であるとされています。
1. 「不適切な行為」の法的位置づけと防止措置
法は、対象事業者が行う調査等の結果、「不適切な行為」が行われたと合理的に判断される場合には、法第6条に定める児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」に該当するものとして取り扱われます。この「おそれ」があると認定された場合、事業者は防止措置を講じる義務があります。
防止措置の内容は、その行為の重大性に応じて段階的に検討され、必要に応じて業務上の配置転換、指導、または従事制限などが求められます。
2. 「不適切な行為」の具体的な例
「不適切な行為」の例には、性暴力等につながる可能性をはらむ、以下のような行為が含まれます。
- 私的なコミュニケーション・面会:児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと。休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと。
- 撮影・管理:私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画の撮影・管理を行うこと。
- 密室・不必要な接触:不必要に児童等と密室で二人きりになろうとすること(用務がないのに別室に呼び出す等)。業務上必要でないのに、児童等に不必要な身体接触を行う(長時間抱きしめる、膝に乗せる等)。
- 特別扱い:特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えること。
3. 事業者に求められる対応と「重大な不適切な行為」
「不適切な行為」の範囲は、事業内容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって異なりうるため、各事業者においてその内容を定め、服務規律等に適切に反映し、従事者に対して周知徹底を行う必要があります。
特に、業務上身体接触を伴う行為を行う必要がある場合(例:スポーツ指導、未就学児との信頼関係構築など)には、児童や保護者に対してあらかじめ説明し、合意形成を図ることが推奨されています。
重大な不適切な行為と判断されるケース
- 反復継続:指導等にもかかわらず、従事者が同様の行為を繰り返す場合。
- 重大な悪質性:執拗に、あるいは児童や保護者の意に反することを認識しながら行うなど、悪質性が高まる場合。
これらの「重大な不適切な行為」については、原則として対象業務に従事させないなど、より厳格な防止措置の検討が求められます。
事業者は、軽微な段階での行為も見逃さず、組織全体で早期対応・記録管理・再発防止策を講じることで、児童の安全と信頼を確保する責務があります。