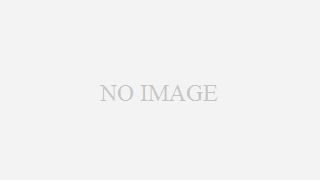いとま特例の定義と重要性
こども性暴力防止法(日本版DBS)における犯罪事実確認は、原則として従事者が業務に従事する前に完了することが求められています。しかし、突発的な欠員や組織変更など、事業者の責めに帰すことができない「やむを得ない事情」がある場合に限り、従事開始後に確認を行うことが例外的に認められています。これがいとま特例(法第26条第2項)です。
この特例の適用には厳格な期限が設けられており、わずか1日でも期限を超過すると、犯罪事実確認義務違反として認定取消し(法第32条第1項第3号)の対象となる重大なリスクが生じます。
厳格な期限管理:原則3ヶ月と最長6ヶ月の境界線
いとま特例における犯罪事実確認の期限は、原則として従事開始日から3ヶ月以内です。これは、急な欠員や予見不可能な利用者増による新規採用といった、多くの通常ケースに適用されます。
しかし、以下のような限定的な事情がある場合に限り、期限が最長6ヶ月まで延長されます。
- 組織変更等による期間延長:合併、事業承継などにより、多数の確認対象者が同時に発生し、事務処理が集中するケース。
- 国側の交付遅延による期間延長:事業者が期限内に十分な余裕をもって申請したにもかかわらず、国から交付が間に合わない場合。
事業者は、これらの「やむを得ない事情」を客観的に証する文書や記録を保存する義務を負います。
特例期間中の安全確保措置の義務
いとま特例の対象となり、犯罪事実確認が完了するまでの間、従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされる状態にあります。この期間中、事業者は児童の安全を確保するための必要な措置を講じる義務を負います。これは防止措置の一環であり、次のような運用を徹底することが求められます。
- 児童等と一対一にさせないことを基本原則とする。
- 個別指導や面談など、やむを得ず一対一の状況が発生しないようシフトや配置を調整する。
- 初動期間は研修業務や補助業務を優先させる。
これらの具体的な安全措置の手順や、いとま特例の適用ルールは、事業者が策定を義務付けられている児童対象性暴力等対処規程に明確に盛り込まれるべき要素です。
まとめ:制度の柔軟性とリスク管理の両立
いとま特例は、急な欠員や組織的事情に対応するための例外的措置であり、その運用には極めて慎重な管理が求められます。事業者は、期限管理・文書記録・安全確保措置を徹底し、制度の信頼性を損なうことのないよう継続的な体制整備を行うことが重要です。