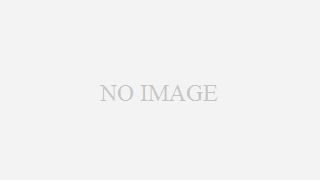犯罪事実確認とは
「犯罪事実確認」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS)において、特定性犯罪事実該当者であるか否かについて、国が事業者に対し情報を提供することで行う確認を指します。
これは、対象事業者が講ずべき主要な安全確保措置の一つであり、教員等や教育保育等従事者が過去に特定性犯罪を犯していないかを確認することを目的としています。
1. 犯罪事実確認の対象者と期限
犯罪事実確認は、対象業務に従事させるすべての者について、以下の期間内に行うことが義務付けられています。
| 対象者 | 事業者種別 | 確認期限(政令で定める期間) | 根拠条項 |
|---|---|---|---|
| 新規採用者 | 学校設置者等・認定事業者等 | 当該業務を行わせるまで | 法第4条第1項、法第26条第1項 |
| 施行時現職者 | 学校設置者等 | 施行日から起算して3年を経過する日まで | 法第4条第3項 |
| 認定時現職者 | 認定事業者等 | 認定等から起算して1年を経過する日まで | 法第26条第3項 |
| 再確認 | 全ての対象事業者 | 確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで | 法第4条第4項、法第26条第6項 |
また、急な欠員などやむを得ない事情により従事までに確認を行ういとまがない場合、いとま特例(法第26条第2項)が適用されます。この場合、従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に確認を行うことが可能です。ただし、この期間中は、その従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければなりません。
2. 犯罪事実確認の具体的な手続の流れ
犯罪事実確認は、原則として「こども性暴力防止法関連システム」を利用したオンラインで実施されます。その手続の流れは以下のとおりです。
- 事業者の交付申請: 対象事業者(学校設置者等または認定事業者等)が、内閣総理大臣(こども家庭庁)に犯罪事実確認書の交付申請を行います。
- 従事者の情報提出: 申請従事者は、氏名・生年月日等の申請対象者情報や、本籍等が記載された戸籍情報等(日本国籍の場合)または本人特定情報(外国籍の場合)を国(こども家庭庁)に提出します。
- 国による照会: 内閣総理大臣(こども家庭庁)が法務大臣(法務省)に対し、特定性犯罪の有無等を照会します。
- 犯罪事実確認書の交付:
・犯歴なしの場合:内閣総理大臣(こども家庭庁)は、申請事業者に対して犯罪事実確認書を交付します。
・犯歴ありの場合:交付前に、従事者本人に犯罪事実確認書に記載する内容を事前通知します。従事者は通知から2週間以内に内容が事実でないと思料する場合、訂正請求を行うことができます。 - 標準処理期間: 交付申請から交付までの目安期間は、日本国籍の場合2週間〜1か月、外国籍の場合1か月〜2か月とされています。
3. 犯罪事実確認記録等の取扱いと情報管理
犯罪事実確認の結果交付される犯罪事実確認書およびその記録(犯罪事実確認記録等)は、目的外利用や第三者提供が原則禁止されています。これらは、厳格な情報管理措置(組織的・人的・物理的・技術的対策)の下で適正に管理されなければなりません。
また、これらの記録を一定期間経過後に廃棄・消去する場合にも、完全消去(クロスカット処理・データ破壊等)を行うことが求められます。情報管理措置の不備や漏えいは、法的責任を問われる重大なリスクとなるため、管理者の選任・運用ルールの文書化が不可欠です。