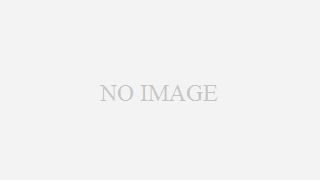児童対象性暴力等とは(法第2条第2項)
「児童対象性暴力等」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS)の対象事業者が、防止措置を講じるべき行為の定義です。この行為は、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に生涯にわたり回復し難い重大な影響を与えることに鑑みて定義されており、以下の二つの要素を含みます。
- 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等。
- 法における「児童等」に含まれる高等専門学校の第1学年から第3学年まで、または専修学校(高等課程)に在学する者に対して行われる、上記1に相当する行為。
児童対象性暴力等の具体的な行為の類型
児童対象性暴力等には、刑法上の特定の性犯罪行為や、迷惑防止条例等で罰せられる行為などが含まれ、その定義は主に以下の5つの類型に分類されます。
- 性交等または性交等をさせること(刑法第177条の不同意性交等罪、児童福祉法第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為など)。
- わいせつな行為またはわいせつな行為をさせること(刑法第176条の不同意わいせつ罪など)。
- 16歳未満の者に対するわいせつ目的の面会要求等(刑法第182条の罪)、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法の罪に当たる行為。
- 児童等を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような行為(例:性的部位等への不必要な接触、盗撮等)。
- 児童等に対する性的羞恥心を害する言動であって、心身に有害な影響を与えるもの(悪質なセクシュアル・ハラスメントなど)。
「不適切な行為」の防止措置への組み込み
対象事業者が防止すべきは、上記の「児童対象性暴力等」に限られません。防止措置(法第6条)の検討においては、児童対象性暴力等には該当しないが、その行為が継続・発展することにより性暴力等につながりうる行為、すなわち「不適切な行為」も対象としています。
「不適切な行為」は、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであり、事業者はこの段階で対処することで未然防止を図ることが重要です。具体的には、以下の例が挙げられます。
- 私的なコミュニケーション・撮影:児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと。または、私物のスマートフォンやルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・管理すること。
- 密室・身体接触:不必要に児童等と密室で二人きりになろうとすることや、業務上必要でない身体接触を行うこと。
- 特別扱い:特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりすること。
事業者は、これらの「不適切な行為」の範囲を服務規律等に明確に反映させ、従事者に周知徹底し、児童等及び保護者とも認識を共有することが求められています。