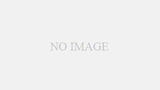こども性暴力防止法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、絶対に防がなければならないという理念に基づき成立しました
学校設置者等(義務)および認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)は、児童対象性暴力等の防止等の責務を負う「対象事業者」であり、次の安全確保措置が課されます。 早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、犯罪事実確認、結果等を踏まえた防止措置です。
特定性犯罪者が職員にいる場合の対応は、その者の犯罪事実該当性や、児童対象性暴力が行われる「おそれ」の内容に応じて、段階的に厳格な措置を取ることが求められます。
おそれの認定と判断プロセス
対象事業者は、犯罪事実確認の結果や児童からの相談、早期把握措置などを踏まえ、児童対象性暴力が行われる「おそれがある」と認められる場合、防止措置を講じなければなりません。
おそれがあると認められる具体例
- 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であった場合
特定性犯罪の再犯リスクは高いことを念頭におく必要があります。そして教育、保育等の現場で児童等に接する業務に従事する適格性を欠くため、通常、この事実をもって「おそれがある」と認めることが適当とされています - 調査の結果、児童対象性暴力が行われたと合理的に判断される場合
被害児童等への更なる加害や被害拡大を防ぎ、業務適格性の観点から「おそれがある」と認められます(事実の確認) - 調査の結果、児童対象性暴力には該当しないが不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合
不適切な行為は、性暴力につながりうる行為(例:児童等とSNSで私的なやり取りを行う、不必要に更衣室等に入室する)が含まれ、合理的に認められる場合は「おそれがある」と認定されます(防止措置へのステップ) - 被害の申出があった場合
在籍する児童等やその保護者から被害の申出があった場合(事実確認の途中であっても)は、被害が拡大する可能性があるため、「おそれあり」と認定され、速やかな接触回避措置を講じる必要があります。
防止措置の判断プロセス
- 事前準備
「児童対象性暴力」および「不適切な行為」の範囲や評価プロセスを明確化し、就業規則等に定めます。 - 端緒の把握
犯罪事実確認結果、早期把握措置、内部通報などにより疑いが生じた場合、些細な情報であっても迅速に事実確認を行います。 - 事実確認(調査)
被害児童や加害が疑われる職員への聴取、監視カメラなどの客観証拠収集を行います。児童等の人権や特性に配慮し、公正かつ中立に調査します。必要に応じて警察や専門家と連携します。 - 事実の評価
収集情報を基に、児童対象性暴力や不適切行為が合理的に認められるか判断します。合理的に認められる場合には、本人の自己申告や証拠の整合性が考慮されます。 - おそれの認定
合理的に認められる事実がある場合、「おそれあり」と認定し、内容に応じた防止措置を講じます。
おそれの内容に応じた防止措置
「おそれ」の内容に応じ、対象事業者は以下の防止措置を講じます。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であった場合
- 原則、対象業務に従事させない
- 新規採用の場合:内定取消し等を検討
- 現職者の場合:対象業務以外への配置転換等を検討
調査の結果、児童対象性暴力が行われたと合理的に判断される場合
- 原則、対象業務に従事させない
- 懲戒事由に該当する場合、就業規則に沿った対応を実施
- 防止措置として不十分な場合、配置転換等を実施
被害の申出があった場合
- 被害児童と加害疑い職員の接触回避
- 一時的措置として自宅待機命令や別業務への従事
- 事実確認後、改めて適切な対応を実施
不適切な行為が合理的に認められる場合
- 重大な不適切行為:対象業務従事不可(児童対象性暴力と同様)
- 軽微な場合:指導や研修受講命令、経過観察
- 再発の場合:より厳格な対応(懲戒等)を実施
労働法制上の留意点
- 新規採用者の場合
犯歴が判明した場合、内定取消しが「重要な経歴の詐称」として合理性を持つ場合があります。事前確認がなかった場合は、別業務での採用なども検討されます。採用の過程で特定性犯罪者ではないこと明示的に確認することが、内定取消しや解雇の合理性・相当性を判断する上で重要とされています。 - 現職者の場合
解雇の有効性は、個別の事案ごとに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性をもって判断されます。配置転換等の措置を十分に検討しても、法に基づく防止措置を行えない場合、普通解雇の有効性の判断において重要な要素として判断の材料となります。 - 派遣労働者や請負労働者
派遣先等(対象事業者)は、犯歴情報そのものを派遣元等に伝えることは法第12条の目的外利用・第三者提供の禁止の違反にあたります。そのため、契約書等に「おそれがある場合」の交代要請に関する規定を盛り込む等の対応が必要です。
その他の重要な措置
犯罪事実確認ができなかった場合
- 期限までに戸籍等を提出しない従事者を対象業務に従事させ続けると、犯罪事実確認義務違反に該当
- 事業者は事前に提出義務を通知
- 提出がない場合、配置転換等の措置を検討
犯罪事実確認記録等の厳格な管理
- 目的外利用・第三者提供の禁止
犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書とそれに記載された情報に係る記録)は、犯罪事実確認または防止措置の実施目的以外の利用・第三者提供が原則禁止されています。違反した場合、罰則(法第43条、第45条第2項)や認定取消しの対象となります。 - 漏えい報告
犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失、き損など個人の権利利益を害するおそれが大きい重大事態が発生した場合、対象事業者は直ちに(概ね3~5日以内)内閣総理大臣(こども家庭庁)に報告しなければなりません。 - 廃棄・消去
犯罪事実確認記録等は、離職の日等から30日以内、または確認日から5年後の属する年度の末日から30日以内に、復元不可能な方法で廃棄・消去することが義務付けられています。違反は罰則の対象です。
情報管理は、組織的、人的、物理的、技術的な観点から策定された情報管理規程を策定・遵守することで満たされるとされています。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。