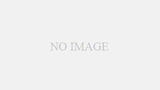いとま特例の期限管理が認定の命運を分ける
いとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に行うことを認める例外措置です。
この特例における確認期限は、原則「3ヶ月」であり、特定の事情がある場合に限り「6ヶ月」に延長されます。
わずか1日でも期限を超過すると、犯罪事実確認義務違反となり、認定取り消し(法第32条第1項第3号)の対象となる重大リスクが存在します。したがって、正確な期限管理と証拠保全が不可欠です。
確認期限「3ヶ月」の適用範囲
3ヶ月が適用されるケースの基本構造
いとま特例が認められる場合でも、原則的な期限は従事開始日から3ヶ月以内です。
この期限は、組織変更や国の交付遅延など特別な事情を除く場合、たとえば急な欠員や予測不能な利用者増による新規採用などに適用されます。
3ヶ月期限の計算開始日
期限の起算日は「当該業務に従事させた日」、すなわち従事者が実際に教育・保育などの対象業務を開始した日です。
従事開始日を正確に特定し、期限日を明確にすることが、認定リスク回避の第一歩となります。
期限延長「6ヶ月」を決定する二大基準
特例期限が6ヶ月に延長されるのは、以下の二つのケースに限定されます。
組織変更等による期間延長
内閣府令では、合併・事業承継などの「組織変更等」によって、多数の従事者を承継し継続的に事業運営を行う場合に6ヶ月延長が認められます。
適用除外となるリスク管理
契約締結日から効力発生日までに十分な期間があるにもかかわらず確認を怠った場合、特例適用が認められないリスクがあります。
事業者は承継スタッフ数と確認期間の計画的な実施義務を負います。
求められる証拠管理
組織変更の事実を証する契約書や組織図変更の記録などを適切に保存し、監督者への報告や立入検査で提示できる状態にしておく必要があります。
国側の犯罪事実確認書交付遅延による期間延長
対象事業者が従事者の従事開始までに十分な余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、交付が受けられない場合に限り6ヶ月への延長が認められます。
「十分な余裕」の法的定義
- 日本国籍従事者:標準処理期間2週間~1ヶ月、1ヶ月を超過して交付がない場合
- 外国籍従事者:標準処理期間1ヶ月~2ヶ月、2ヶ月を超過して交付がない場合
求められる証明手段
事業者は、交付申請が遅滞なく行われたことを証明するために、申請システム上の記録や、従事者に対する戸籍関連情報提出の通知など、事業者の責めに帰すべき遅延がなかったことを明確にしておく必要があります。
実務上のリスク管理:3ヶ月から6ヶ月への再延長
混合ケースの対応
当初は急な欠員などで3ヶ月期限が適用されていた職員について、期限内に申請手続きを行ったにもかかわらず、国からの交付が間に合わない場合、期限は6ヶ月に延長されます。
この場合、事業者側が期限までに申請を完了させていた証拠が不可欠です。
事業者の責めに帰す事情の回避
従事者が戸籍関連情報を提出せず申請が遅れた場合、国の交付遅延による6ヶ月延長は認められません。
このリスクを回避するため、事業者は内定通知や異動内示などの意思表示を行った時点で、犯罪事実確認の必要性やスケジュール、従事者が行うべき事項を事前に書面で通知する義務があります。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
[polaire_jsonld_auto
title=”いとま特例の期限管理ガイド:3ヶ月と6ヶ月の境界線と証拠保全の実務 “
desc=””]