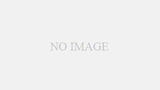犯歴情報管理のパラダイムシフト
こども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。
確認書の管理において、法が目指すのは管理の厳格化であり、その手段としてデジタル化の徹底が採用されています。
具体的には、確認書の交付は法関連システム上での閲覧を原則とし、情報の転記や電子ファイル化、紙での保存・伝達・利用は極力避けることが求められています。
閲覧原則の実現とデジタル化の構造
システム上での交付と閲覧の仕組み
犯罪事実確認書の交付申請から交付まで(本人通知を含む)は、原則として法関連システム上で行われます。交付された確認書も画面閲覧のみ可能とされています。
事業者は、法で定める期限内にシステムにログインすることで、いつでも確認書を閲覧することができます。この仕組みにより、紙や電子ファイルとして情報を保有する必要性は低減されます。
情報管理の基本原則との関連
閲覧原則は、情報管理規程に盛り込むべき「犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること」を具体的に実現する措置です。
記録・保存を避けることで、機微情報が漏えいした場合の個人の権利利益への影響を最小限に抑えることができます。
厳格な情報秘匿を担保するシステムの工夫
確認書の様式(氏名不記載)
確認書が万が一漏えいした場合に備え、本人を特定できる氏名等は記載せず、法関連システム上の管理番号(申請番号)のみを記載します。
事業者は、氏名等の申請対象者情報と申請番号を別途管理簿等で照合して本人を特定します。
内部共有時の安全性確保
同一事業者内での伝達や利用においても、閲覧権限を付与された者のみがシステムにログインして確認できるようにします。
県費負担教職員、施設運営者、共同認定の場合の事業者間での情報共有も、システム内の権限設定によりアクセス制限をかけます。
防止措置は、事業者内で完結する場合は情報を不必要に共有しないこととされています。
「極力行わない」原則への違反リスク
やむを得ない場合の厳格な管理
やむを得ず確認記録等を記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を実施する必要があります。
電子ファイルや紙の記録を作成した場合、当該情報は「犯罪事実確認記録」とみなされ、法第38条に基づき廃棄・消去義務を負います。
法令違反と事業運営への影響
犯罪事実確認記録等の適正管理義務(法第11条、第14条)に違反し、漏えい等が認められた場合、国は是正命令を発することができます。
是正措置が講じられるまで、当該事業者の新規交付申請は停止され(法第35条第3項)、採用や再確認手続きが停滞することになります。
廃棄・消去を怠った場合には罰則が科されます。
まとめ
法関連システムによる閲覧原則は、犯罪事実確認書が事業者の管理外に置かれるリスクを最小化し、情報管理の安全性確保と事務負担軽減を両立するデジタル戦略の核です。
事業者は、この原則を徹底し、可能な限りシステム外で情報を保有しないことが、法令遵守の最も確実な方法となります。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
[polaire_jsonld_auto
title=”DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務”
desc=””]