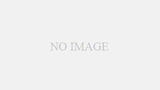「こども性暴力防止法」では、児童対象性暴力等を未然に防止するため、学校設置者や認定事業者に対して早期把握の義務が定められています。ここでは、内閣府令で定められる予定の具体的措置として、日常観察と発達段階や特性に応じた面談・アンケートの内容を整理します。
児童等に対する日常観察の具体的内容
日常観察の目的と基本方針
日常観察は、児童等の心身や行動の変化を日常的に把握することで、性暴力が行われるおそれを早期に発見することを目的としています。観察対象は心身の状態、行動パターン、情緒の変化など幅広く設定されます。
観察の着眼点
日常観察で特に留意すべき心身・行動の変化の例は以下の通りです。特に言葉による意思表示が難しい年齢の幼児等については、日ごろからの観察が重要視されています。
- からだの変化
体調不良(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など)、過呼吸、動悸、過度な発汗、不眠(怖い夢や睡眠中の叫び声)、食欲不振・過食、排泄トラブル(頻尿、夜尿、下痢など) - こころの変化
元気の消失や過剰な元気、情緒不安定、集中力の低下、学力不振、イライラ、自信喪失、自己卑下 - 行動面の変化
人との距離の変化(接触回避・過剰接近)、身体接触や肌の露出を嫌がる、性的な話題や行動の変化、反抗的・乱暴な行動、非行(飲酒・喫煙・家出)、自傷行為、特定の人物への過度な避け・接近
※これらの変化は必ずしも性暴力被害を示すものではなく、他の要因で生じる場合もあります。
日常観察の実施上の留意点の例
- 複数名での観察:児童に最も身近な者が加害者である可能性を考慮し、可能な限り複数名で観察する
- 声掛けの実施:変化を察知した際には、積極的に声掛けして対話に繋げる
- 継続的対応:被害の即時開示がない場合も継続的に声掛け等を行う
- 環境づくり:従事者間および児童との間で気づきや違和感を共有しやすい雰囲気を整える
- 研修での周知:従事者が観察すべき変化を研修教材に取り入れる
- 未就学児や障害児への対応:意思疎通が困難な児童では日常観察の重要性がさらに高まる
発達段階や特性に応じた定期的な面談・アンケート
面談・アンケートの目的
児童の発達段階や特性に応じた面談やアンケートを定期的に行うことで、性暴力に関する悩みや被害の兆候を早期に把握し、適切な支援や防止措置につなげることが目的です。
発達段階・特性別の対応例
- 未就学児
面談やアンケートは困難なため、日常観察を中心とし、必要に応じて保護者への質問を併用 - 小学生
面談・アンケートに先立ち、質問内容の説明や児童への権利・性に関するルールの学習を行い、その過程で実施 - 障害児
可能な限り児童自身が回答できるよう工夫し、回答補助は担当従事者以外が行うことが望ましい
知的障害のある児童には、定期面談も有効
実施上の留意点
- 定期的な実施:常に悩みを打ち明ける機会を確保し、加害行為の抑制効果も期待
- 既存アンケートとの併用:児童負担を軽減するため、既存アンケートに性暴力関連の設問を追加
- 回答者の保護:回答者が特定されないよう回収・閲覧権限を管理
- トラウマへの配慮:既被害児童がフラッシュバックしないよう、回答中止の選択肢や相談窓口の案内を提供
[polaire_jsonld_auto
title=”こども性暴力防止法における早期把握の具体的措置”
desc=”こども性暴力防止法における早期把握の具体的措置として、日常観察や発達段階・特性に応じた面談・アンケートの内容を解説。児童の心身・行動変化に着目した観察方法や、障害児・未就学児への配慮など専門的に整理。”]
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。