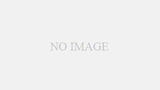内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を占め、交際相手・元交際相手より高い割合となっています。
教育・保育の場での加害は、児童が信頼する大人からの裏切り行為であり、心理的負担は非常に大きくなります。性暴力は身体面(頭痛、腹痛、不眠など)や心理面(抑うつ、不安障害、フラッシュバックなど)に長期的影響を及ぼし、日常生活や人間関係の形成に支障をきたす場合があります。
被害の発見が困難な背景
児童は、性暴力被害を「思い出したくない」「誰にも知られたくない」「恐怖で口に出せない」と感じることが多く、相談や開示が非常に困難です。家庭環境、障害の有無、男児である場合の羞恥心なども、発見の難しさを増幅させます。
特に学校関係者からの加害は、信頼関係の裏切りとなるため、被害を訴える心理的ハードルはさらに高くなります。男児の場合は「男の自分が被害を受けるはずがない」と思い込み、羞恥心や自責から声を上げにくくなります。障害のある児童は、被害を認識したり周囲に伝えたりすることが難しく、支援者との関係が崩れると生活への影響も懸念されます。また、家庭内に不和や虐待がある場合は、加害者からの報復や庇護喪失の恐怖から、被害の訴えが一層困難となります。
教育・保育の場における性暴力は「支配性」「継続性」「閉鎖性」といった特別な性質を持ち、信頼と権力の濫用が被害の発見を難しくしています。
大人たちの目と社会的責任
性暴力の未然防止と早期発見には、児童を取り巻く大人の注意と関心が不可欠です。児童の変化や困惑の兆しに気づき、声をかけ、適切な相談・支援につなげることは、性暴力被害を防ぎ、潜在化を防ぐ上で重要です。
教育現場の従事者自身も、性暴力防止の啓発や研修を継続的に行うことで、加害の芽を早期に摘むことが可能です。日頃から児童の心身の状況や言動に目を配り、体調不良、情緒不安定、特定の人物との関係の不自然さなど、小さな変化やSOS信号を見逃さない努力が求められます。
従事者への研修では、性暴力が「生じ得る」との認識を持ち、自分ごととして考える機会を設けることが重要です。ケーススタディやワークショップなどを通じて、児童への性暴力加害の抑止や、疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見につなげます。
啓発と行動のポイント
児童の変化に敏感になり、適切に対応する
日常の観察や会話を通じて、児童の微細な変化に気づき、必要に応じて声をかけることが重要です。
安心して話せる環境の整備
性暴力の疑いがある場合、児童が安心して話せる場所に移動し、傾聴します。「あなたは悪くない」と伝え、非難に聞こえる質問を避けるなど、心理的安全性に配慮した対応が求められます。疑いの段階から問題を重く受け止め、組織防衛心理による放置や隠蔽は避ける必要があります。
性暴力防止研修の実施
全ての従事者に対し、児童への性暴力加害の抑止や疑いが生じた場合の対応に関する研修の機会を確保することが求められます。
家庭や地域社会での支援ネットワーク
学校・保育事業者は、警察、性暴力被害者支援機関、医療機関、児童相談所などの関係機関と連携して支援を進めることが重要です。保護者に対しても、性暴力に関する知識や、被害時の児童への接し方(児童を責めず、記憶の汚染を防ぐため非専門家による詳細な聴き取りは控えるなど)についての情報提供と啓発を行うことが推奨されます。
出典:教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(PDF/6.8MB)
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
[polaire_jsonld_auto
title=”児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性 “
desc=”学校や保育の場における児童性暴力の現状と深刻さ、発見の困難さ、社会的責任、早期発見・未然防止の具体的取り組みを解説。教育現場での注意点や日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく対応も含む専門記事。”]