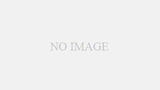「こども性暴力防止法」(以下「法」)に基づき、学校設置者等や施設運営者、認定事業者等(以下「対象事業者等」)は、犯罪事実確認や安全確保措置の実施状況について、国や所轄庁への定期的な報告義務があります。本記事では、国(こども家庭庁)および所轄庁への報告内容を簡潔に整理します。
1. 国(こども家庭庁)への定期報告
対象事業者等は、犯罪事実確認の実施状況や情報管理措置の実施状況について、内閣府令で定められた事項を国に報告します。認定事業者等はさらに、その他の安全確保措置の実施状況についても報告する必要があります。
報告内容
| 報告項目 | 対象事業者 | 具体的な報告事項 |
| 犯罪事実確認 | 犯罪事実確認実施者等、 認定事業者等 | ・報告期間中に対象業務従事者として登録されていた者の一覧(未完了・離職者含む) ・各従事者の申請区分(新規・施行時現職者・5年後再確認)や状況(離職の有無、従事の有無、施設区分など)、従事開始日、確認期限、確認日/受領日、「いとま特例」の適用状況 ・施設・事業所ごとの確認対象者数および実施済件数、特定性犯罪該当者数、「いとま特例」適用者数 |
| 情報管理措置 | 犯罪事実確認実施者等、認定事業者等 | 事業区分ごとの情報管理措置の実施状況 |
| その他安全確保措置 | 認定事業者等のみ | 事業区分・施設ごとの安全確保措置の実施状況 |
報告の頻度・時期
- 犯罪事実確認実施者等:毎年4月末日を基準日とし、5月末日までに報告(初年度は令和10年5月末が初回期限)
- 認定事業者等:認定日から1年経過の前日を初回期限、その後1年ごとに報告
- 方法:原則オンラインで実施
2. 所轄庁への定期報告
所轄庁は、学校教育法や児童福祉法などの各業法に基づき、事業者の安全確保措置の監督を行うため、定期報告を求めます。報告内容は国への報告内容を参考としつつ、所轄庁の判断で求められることがあります。
想定される報告事項
| 報告項目 | 想定される内容 |
| 犯罪事実確認 | 各施設・事業所ごとの確認対象者数、実施済件数、特定性犯罪事実該当者数、いとま特例適用者数 |
| その他安全確保措置 | 事業区分・施設ごとの安全確保措置の実施状況 |
※ 所轄庁への報告の頻度・時期は、可能な限り国への報告に合わせることが推奨されます。
まとめ
- 「こども性暴力防止法」に基づき、対象事業者等は国・所轄庁への定期報告義務があります。
- 国への報告は犯罪事実確認、情報管理措置、安全確保措置の実施状況が中心です。
- 所轄庁への報告は国の報告内容を参考に、安全確保措置の監督のため行われます。
- 報告は原則オンラインで、事業者は報告期日を遵守する必要があります。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
[polaire_jsonld_auto
title=”事業者の定期報告義務|こども性暴力防止法に基づく国・所轄庁への報告”
desc=”行政書士が解説。こども性暴力防止法に基づく事業者の国・所轄庁への定期報告義務について、犯罪事実確認や安全確保措置の実施状況をわかりやすく整理しています。”]