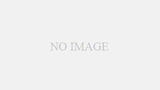2024年に成立した**日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育の現場で「児童対象性暴力等を未然に防止するための仕組みづくり」が義務付けられました。
その中でも特に重要なのが、安全確保措置①に位置付けられている「早期把握(早期発見)」**です。
本記事では、行政書士の立場から、この「早期発見」の仕組みを整理してご紹介します。
早期把握措置の義務付け
法律では、学校設置者や認定を受けた民間教育保育等事業者に対して、次のことが義務付けられています。
- 教員等による児童対象性暴力が行われるおそれを早期に把握するための措置を実施すること(法第5条第1項、法第20条第1項第2号)。
- この措置の内容は、内閣府令で具体的に定められることとされています。
つまり、形式的なチェックではなく、現場の児童一人ひとりを日常的に見守り、違和感やサインを早めに察知する体制づくりが求められているのです。
内閣府令で定められた具体的な「早期発見」の内容
内閣府令では、早期に把握するための措置として、以下の3つが明示されています。
- 日常観察
- 定期的な面談・アンケート
- 適切な報告・対応ルールの策定・周知
これらを組み合わせ、子どもたちが安心して声をあげられる環境を整えることが必須です。
実施にあたっての留意事項
(1)日常観察
- 教員や従事者は、児童の心身・行動に変化がないかを日常的に観察します。
- 一人の目ではなく、複数名で観察することが望ましいとされています。
- 小さな違和感でも共有し、声かけや対話につなげることが重要です。
- 特に未就学児や意思疎通が難しい障害児については、日常観察の重要性が強調されています。
(2)定期的な面談・アンケート
- 発達段階や障害の有無に応じて、面談やアンケートを工夫して実施します。
- 未就学児の場合は保護者との面談・アンケートを活用することも有効です。
- 障害のある児童には、回答を補助しながら、可能な限り本人の声を聞く工夫が求められます。
(3)報告・対応ルールの策定と周知
- 不適切な行為を把握した場合の報告ルートや手順を明確化します。
- 権限を持つ従事者が関与しているケースも想定し、匿名通報窓口や外部窓口の周知も必要です。
- 相談や通報を理由に不利益を与えてはならないことが強調されています。
まとめ
「早期発見」は、子どもを守るために不可欠な取り組みです。
しかし、日常観察・面談・通報ルールの整備など、現場で実際に形にしていくには専門的な知識と運用体制が必要となります。
行政書士事務所として
- 事業者が認定を受けるための体制づくり
- 報告・通報ルールの策定支援
- 従事者向けの周知資料の作成
などのサポートをいたします。 法の施行まであと1年と少しを残すのみとなりました。
事業所の準備や仕組みづくりでお悩みの事業所様を、法律の施行前からご支援致します。 どんな小さなことでも構いません。お気軽にご相談ください。
※執筆時点の情報です。最新の内容については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
[polaire_jsonld_auto
title=”日本版DBSと早期発見の義務|安全確保措置①を行政書士が解説【熊本・合志市】”
desc=””日本版DBS(こども性暴力防止法)の安全確保措置①「早期発見」について行政書士が解説。日常観察・面談・報告ルールを中心に、熊本・合志市の事業者向けに分かりやすく説明します。”]