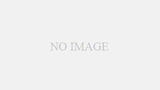日本版DBS(こども性暴力防止法)における民間教育保育等事業者と事業運営者が連携して受けることができる「共同認定」の制度について、その定義、役割分担、責任、申請手続きについて整理します。
本記事は、こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)中間とりまとめ案より抜粋して作成しています。
1. 共同認定の定義と目的
共同認定とは、民間教育保育等事業者と事業運営者が、事業運営者の管理する事業所で行われる民間教育保育等事業について、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を共同で受けることができる制度です。
- 事業運営者の定義
民間教育保育等事業者から地方自治法に基づく指定や委託を受け、事業所を管理する者を指します。施設の単なる維持管理のみを担う場合は該当しません。
2. 事業者間の役割分担
共同認定を受ける際、民間教育保育等事業者と事業運営者は、法令で特別に定める事項を除き、契約や指定管理協定に沿って役割を決定できます。ガイドラインでは、以下のような役割分担例が示される予定です。
- 犯罪事実確認
それぞれが雇用する者について、自ら実施します。 - 防止措置
- 民間教育保育等事業者:自らの雇用者に対して人事権に基づく措置(配置転換など)を実施。また、事業運営者の雇用者について悪質な事案が発生した場合、指示を行います。
- 事業運営者:自らの雇用者に対して人事権・現場管理権に基づく措置を実施。民間教育保育等事業者の雇用者には現場の服務監督権に基づく措置(例:子どもと1対1にさせない)を行います。
- 犯罪事実確認記録の情報提供
防止措置のために必要な範囲で互いに提供可能です。 - 早期把握・相談・調査・保護・支援・研修
両者が連携して実施し、事前に役割分担を定めます。例として、早期把握や相談は児童に近い事業運営者が担当し、報告を受けた民間教育保育等事業者が対応を検討する進め方があります。 - 情報管理措置
保有する犯罪事実確認記録等をそれぞれ管理します。 - 定期報告等
国への定期報告や届出は、どちらかが作成し、他方が確認後に提出します。役割分担が変わった場合は報告が必要です。
3. 共同認定における責任と欠格要件
共同認定が取り消された場合、その効果(欠格要件を含む)は民間教育保育等事業者および事業運営者の双方に及びます。
- 例:事業運営者の行為で認定が取り消された場合、民間教育保育等事業者も欠格期間が生じ、2年間は他の事業で認定を受けられません。
※お互いの責任が事業運営に与える影響は大きいため注意が必要です。
4. 共同認定の申請手続き
- 申請方法
民間教育保育等事業者と事業運営者の共同申請によります。 - 申請書記載事項
- 民間教育保育等事業者の情報
- 事業運営者の氏名・名称、住所・所在地
- 事業所の名称と所在地、業務概要
- 添付書類例
- 事業者や業務の詳細説明資料
- 認定基準に適合していることを証する資料(両者の役割分担を含む)
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- 処理期間
通常1〜2か月程度 - 提出方法
原則オンライン。両者が内容を確認・合意した上で提出します。
まとめ
共同認定は、民間教育保育等事業者と事業運営者が連携して、児童の安全確保を図るための制度です。役割分担や責任範囲を明確化することで、認定の取得・維持が円滑に進む仕組みになっています。
※執筆時点の情報です。最新の内容については直接お問い合わせください。
[polaire_jsonld_auto
title=”「こども性暴力防止法」における共同認定とは?仕組みと実務上のポイント”
desc=”熊本・合志市の行政書士が解説する、こども性暴力防止法における共同認定の仕組み。民間教育保育等事業者と事業運営者の役割分担、責任、申請手続きの流れを整理しました。”]
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。