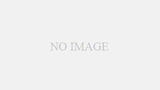日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける制度が導入されます。認定は、学校設置者に求められる安全確保措置と同等の体制が事業者に備わっていることを確認するものです。中間とりまとめ案に基づき、実務で押さえておくべきポイントを整理します。
認定の全体像(根拠)
法第20条第1項に基づき、認定を受けるには複数の要件に適合することが必要です。具体的な運用は内閣府令やガイドラインで示されますが、事業者が今から準備すべき主要項目は次の通りです。
1.犯罪事実確認を適切に実施する体制の整備
- 新規採用時・認定時・5年ごとの再確認など、法で定められた確認が遅滞なく実施できること。
- 犯罪事実確認事務の責任者(担当者)の選任。
- 対象従事者への事前通知、確認書類の適正な保存管理。
- 「いとま特例」適用時の書類保存や説明義務を含めた手順の整備。
実務チェックリスト(例):確認フロー図、担当者名簿、確認書テンプレート、保存ルール。
2.児童の状態変化を早期に把握する措置
- 日常観察の仕組み(複数人での見守りの運用ルール含む)。
- 発達段階や特性に応じた定期的な面談・アンケートの実施計画。
- 変化を捉えた際の報告経路と対応ルール(誰に、どのように報告するか)の明確化。
ポイント:観察記録の様式化と、記録を確認する責任者の設定。
3.相談しやすい体制の整備
- 事業者内の相談員の選任または相談窓口の設置と周知。
- 外部相談窓口(専門機関等)の案内・掲示。
- 年齢・特性に応じた複数の相談チャネル(対面・匿名窓口・保護者向け案内等)。
注意点:児童が相談に至りやすい導線(場所、言葉掛け、時刻)を実務で検証すること。
4.「児童対象性暴力等対処規程」の作成
- 規程に必須の3項目:防止措置/調査の手順/被害児童の保護・支援。
- 学校設置者に求められる措置と同等水準であること(ガイドラインで例示予定)。
- 規程改定時は原則として内閣総理大臣への届出が必要となる点の認識。
実務対応:現行規程の有無を確認し、ギャップ分析→修正案作成→届出フロー準備。
5.従事者向け研修の実施
- 必須科目(例):こどもの権利、発生要因、行為の範囲(盗撮等含む)、早期発見、相談・報告対応、被害児童の支援。
- 座学+演習での実施、定期的なリフレッシュ研修、外部専門家の活用を推奨。
実務Tip:研修履歴の保存、外部講師との契約書・評価記録を揃えておく。
6.情報管理措置の実施
- 犯罪事実確認記録等は取扱者最小化・保存回避を基本とする情報管理規程を策定。
- 管理措置は組織的・人的・物理的・技術的の4観点で整備。
- 「標準的措置」と「最低限求められる措置」の2段階の基準が想定され、情報管理責任者を含む2名以上の体制が必要。
留意点:アクセスログ、認証・権限管理、廃棄・消去ルールまで文書化すること。
実務上の優先順位(私見)
- 犯罪事実確認のフローと責任者の確定(書面化)
- 情報管理規程の初期整備(最低限の技術的措置を実装)
- 相談窓口の設置と周知(児童が使える導線確保)
- 研修計画の確定と初回実施
- 対処規程の草案作成と届出準備
まとめ(結び)
中間とりまとめ案は、民間事業者に対して実務的に何を揃えるべきかを明確に示しています。現場で最初に手を付けるべきは「実施可能なフロー(誰が何をいつ行うか)」の整備と、それを支える情報管理体制です。
現状の文書や運用がある場合は、今回の6項目に沿ってギャップ分析を行うことをおすすめします。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。